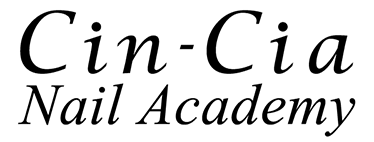【2024年】ネイリストが選ぶジェルネイル5選!セルフ向き人気トレンドメーカーは?
近年、オンラインで購入できるジェルネイルキットが増え、セルフジェルネイルが一般化しています。
なかにはワンコインで購入できる安価なアイテムもありますが、成分によってはリスクがあることをご存知でしたか?
今回ご紹介するネイリストおすすめのメーカーを参考にして、安全にジェルネイルを楽しみましょう。
目次
セルフネイルはソフトジェルがおすすめ!

ジェルネイルは、大きく区分するとハードタイプとソフトタイプの2種類があります。
| ハードジェル | ソフトジェル | |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
硬いハードジェルは筆に取りづらく、ネイル初心者には取り扱いが難しい製品です。
一方、ソフトジェルは自然とジェルが広がるセルフレベリングの力を使えるため、初心者でも難なく塗りやすいでしょう。
また、溶剤でオフできないハードジェルは、ネイルマシーンを持たないセルフネイラーには不向きです。
オフのしやすさも考慮して、セルフネイルではソフトジェルを選びましょう。
初心者がセルフネイルで準備するものとは?基本の道具やジェルネイルの塗り方まで紹介◎
ネイリストが選ぶジェルネイル5選

ジェルネイルは数多くのメーカーで取り扱われ、JNA検定試験用の指定商材だけでも70以上のブランドがあります。
メーカーごとにテクスチャー・機能性・発色などが異なるものの、種類が多すぎて選びきれない人もいるでしょう。
そこでこちらでは、セルフネイルにもおすすめできるネイリストご用達ブランドを5つご紹介します。
プリジェル(PREGEL)
プリジェルはプロ・アマチュア問わず人気の高い有名ブランドです。
柔らかいテクスチャーで取り扱いやすく、硬化熱が出にくい点は大きなメリットでしょう。
発色・密着性・ツヤ感どの要素においてもレベルが高く、長年愛用しているネイリストも多数います。
すべてのジェルネイルが化粧品登録されているため、ネイルサロンで活用しやすいことも人気の理由といえます。
パラジェル(para gel)
パラジェルは爪を削るサンディングの過程が不要なジェルです。
ネイルサロンのHPや予約サイトにて「パラジェル取り扱い店舗」と表記されることも多く、お客様からの人気の高さがうかがえます。
自爪が薄い人やサンディングに不安がある人は、爪にやさしいパラジェルを選ぶと良いでしょう。
カルジェル(Calgel)
カルジェルは2000年代のジェルネイルブームを牽引したブランドのひとつです。
値は張るものの、ジェルネイル講習でも使用される確かな品質には価値があります。
ジェルネイルの使用期限が1〜2年程度であることを考慮すると、コストパフォーマンスは決して悪くありません。
特に、ベースジェルやトップジェルのような毎回使用するクリアジェルがおすすめです。
バイオスカルプチュアジェル(Bio SCULPTURE Gel)
バイオスカルプチュアジェルは世界で初めて誕生した溶剤で溶かせるソークオフジェルです。
創業時から爪の健康に配慮した商品を展開しており、今も世界各国のネイリストに愛用されています。
機能性を重視しているため、つけ心地は軽やかでジェルで覆われた爪でも息苦しさを感じません。
同ブランドのクリアジェルなら、スカルプネイルも地爪のようなナチュラルな仕上がりを実現します。
シャイニージェル(SHINYGEL)
シャイニージェルは弱酸性にこだわったネイルブランドです。
通常、ジェルは酸性が強いほど爪と密着しますが、シャイニージェルは独自の製法で水分で密着度を高める製品を開発しました。
水に強いジェルは、水仕事でネイルが剥がれやすい主婦さんにぜひ試してほしい商品です。
なお、セルフ向けの商品は楽天やAmazonなどの身近な通販サイトから購入可能で、セルフネイラーにやさしいブランドといえるでしょう。
スターターセットも豊富に展開しているため、一度ジェルネイルを試したい人にも、本格的にネイルを学びたい人にもおすすめできます。
▶︎【期間限定】今なら受講料20〜30%免除!ネイルスクールシンシア見学を申し込む
化粧品と雑貨品ジェルの違い

化粧品は皮膚に塗布するものとして、国の規定を満たす必要があります。
- 全成分が表記されている
- 製造元・販売元を表記する
- 皮膚に直接触れても効果・効能が緩和なもの
これらの規定を満たしたものは国から製造を許可され、「化粧品」と表記できます。
一方、「雑貨品」は正式な登録がされていないものですが、一概に品質が悪いわけではありません。
化粧品登録には莫大な費用と時間がかかるため、品質が良くても登録ができていないだけのメーカーもあります。
ただし、化粧品のように安全は保障されないため、トラブル発生の懸念がある点は留意しましょう。
なお、国のガイドラインでは爪に直接塗布するジェルは化粧品利用が必須ですが、爪に直接触れない場合は雑貨品を利用しても良いとされています。
ベースジェルは化粧品表記されたものが望ましいですが、カラージェル・トップジェルは必要に応じて雑貨品を検討しても良いでしょう。
参考:特定非営利活動法人日本ネイリスト協会 「ジェルネイル製品」表示ガイドライン
未硬化ジェルネイルを拭き取らないとどうなる?正しいやり方と失敗例
ジェルネイルは国産化粧品がおすすめ!

ジェルネイルを購入する際は、原産国にも注目しましょう。
セルフネイル向けに販売されている安価な商品は、海外製が中心です。
もちろん質の良い海外メーカーもありますが、なかには爪に刺激が強い成分を含有している製品もあります。
ジェルネイルは約1ヶ月つけたままの状態になるため、長期間身体に悪い成分を付着させることは危険です。
爪トラブルが起きたり、グリーンネイルになる可能性もゼロではありません。
一方、高品質な国産商品は高価な傾向にありますが、劣化の早い製品を買い替えて使うなら国産品のほうがコスパが良いでしょう。
爪の健康のためにも、ぜひ原産地や成分が明確な純国産化粧品を選んでください。
セルフで簡単!グラデーションネイル基本のやり方と応用デザインに挑戦
コンテナジェルとボトルジェルの違い

100円ショップやバラエティショップでは、マニキュアのようなボトルタイプのジェルネイルを中心に取り扱っています。
しかし、ネイルサロンではコンテナタイプを使用するネイリストが多く、どちらを使うべきか悩んでいませんか?
それぞれのメリット・デメリットを把握して、自分に適した形状を選びましょう。
コンテナタイプのメリット&デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
コンテナタイプのジェルネイルは、プロネイリストもよく使用する形状で、ネイルアートを本格的に楽しみたい人に適した製品です。
ジェルネイル専用の筆(ブラシ)を別途用意する手間はありますが、オーバル筆・平筆・細筆など、形を変えればアートの幅がぐっと広がります。
カラージェル同士を皿の上で混ぜれば、オリジナルカラーを楽しめるでしょう。
ボトルタイプのメリット&デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
柔らかいテクスチャーのボトルタイプは、マニキュア感覚で塗りやすく初心者に適しています。
別途ジェルネイル専用の筆(ブラシ)を購入する費用・手間を省けるため、手軽にはじめやすい点も魅力です。
ただし、繊細なネイルアートには不向きでジェルネイルに慣れると物足りなさを感じるでしょう。
ボトルタイプは単色塗り用に購入することをおすすめします。
ノンワイプジェルとは?

ノンワイプジェルとは、未硬化ジェルの拭き取りが不要なジェルのことです。
通常のトップジェルは最後に未硬化ジェルを拭き取る必要がありますが、ノンワイプジェルなら硬化だけでネイルが完成します。
ノンワイプジェルのメリット&デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
ノンワイプジェルはサラッとしたテクスチャー。爪に塗りやすい一方、皮膚に流れ出やすい性質があります。
皮膚についたジェルネイルを硬化すると皮膚トラブルの元となるため、塗布する際は少量で薄く塗ることを意識しましょう。
内側から外側まで完全に硬化する分、硬化熱が発生しやすいデメリットもこの工程でカバーできます。
トレンドのアートにも応用しやすいノンワイプジェルは、使い方に注意しながら活用してください。
▶︎【期間限定】今なら受講料20〜30%免除!ネイルスクールシンシアの見学を申し込む
ネイリストが選ぶおすすめジェルネイル「爪に優しいメーカー」はどれ?
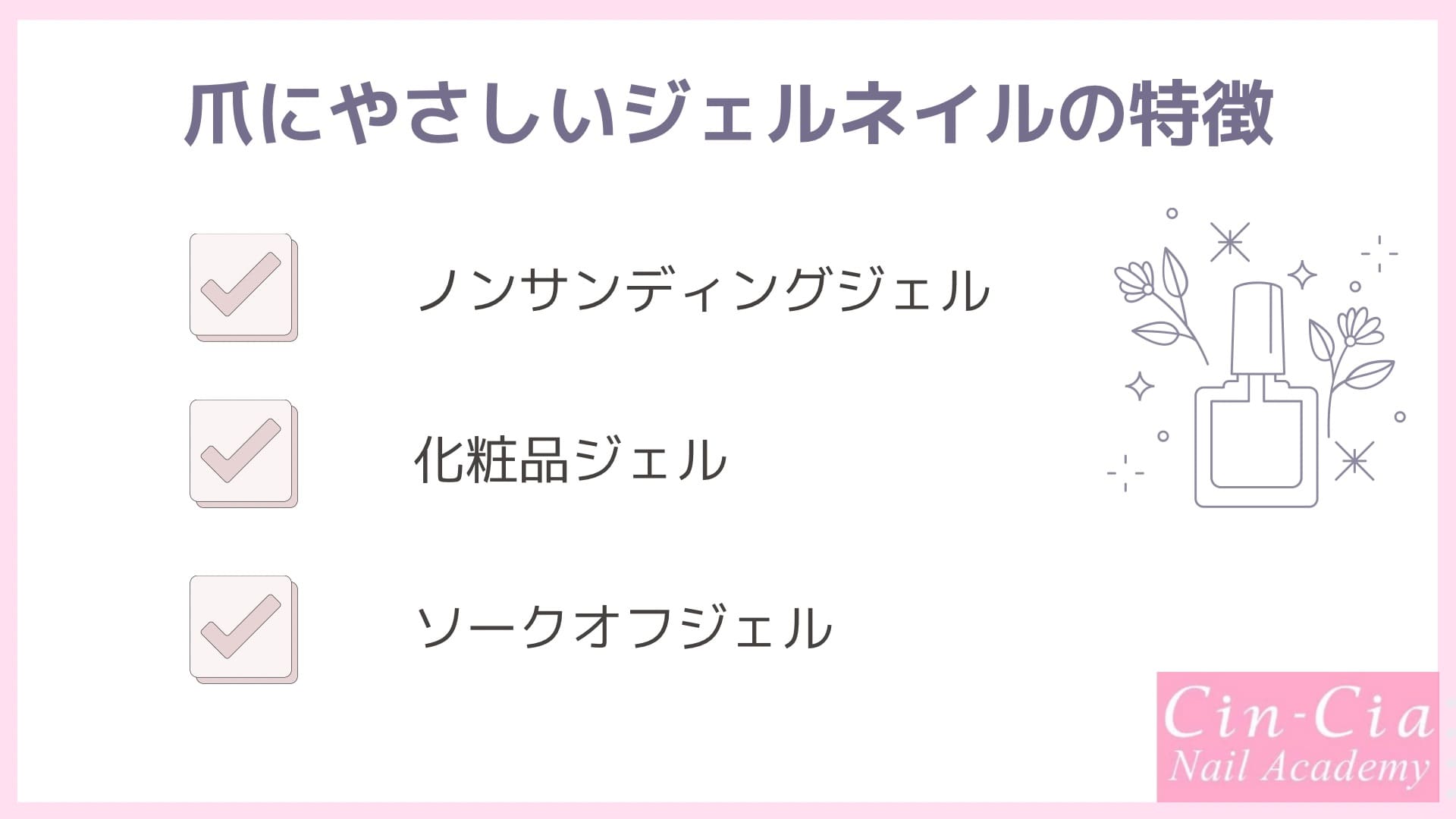
- ノンサンディング
- 化粧品ジェル
- ソークオフジェル
爪に直接塗布するベースジェルは、上記3つの項目を満たす製品を選びましょう。
国の基準を満たした化粧品ジェルなら、爪への刺激も弱く安心して使用できます。
さらに純国産製品にこだわるならプリジェルやシャイニージェル、ナチュラルで健康的なつけ心地にこだわるならバイオスカルプチュアジェルを検討してください。
パラジェルとは? 持ちが悪い原因と正しいオフや使い方・ジェルネイルとの違いを解説
ネイリストが選ぶおすすめジェルネイル「オフしやすいメーカー」はどれ?

- ソフトジェル
- ソークオフジェル
- 溶剤の浸透が早いジェル
爪との密着度が高いハードジェルは、溶剤で溶かせずオフがしづらい製品です。
表面をファイルで軽く削り、後は溶剤で溶かせるソークオフジェルを選べば、手の疲れを軽減できるでしょう。
さらに、ジェルに適した溶剤なら内側まで浸透しやすく、オフのしやすさも格段にあがります。
カルジェルは保湿成分が含まれた専用溶剤を開発しているため、ジェルネイルとセットで購入すると良いでしょう。
ネイリストが選ぶおすすめジェルネイル【購入前の注意点】

基本的にセルフジェルネイルは好きなメーカーを選んで問題ありません。
しかし、検定試験合格やプロを目指すなら、はじめからライトやジェルもこだわって選びましょう。
以下ではジェルネイルライトの種類ごとの特徴や、試験用に適した商材について解説します。
ジェルネイル用ライトの種類について
ジェルネイル用ライトは、主にUV/LED/MIXタイプの3種類があります。
| UVライト | LEDライト | ハイブリット(MIX)ライト | |
| 硬化時間 | 約2〜3分 | 約15〜30秒 | 約30〜60秒 |
| 使用できるジェル |
|
|
|
| 特徴 |
|
|
|
使用するジェルによって対応ライトが異なるため、使いたいジェルに合わせてライトを購入しましょう。
2000年代のジェルネイルブームではUVライトが一般的でしたが、現代のネイルサロンではLEDまたはMIXライトが主流です。
硬化時間を短縮する分ネイルアートに時間をかけられるため、よりレベルの高いネイルを目指せるでしょう。
JNAジェルネイル技能検定試験は「指定商材」を使用する
JNAジェルネイル技能検定試験を受験するなら、はじめから指定商材を購入して取り扱いに慣れましょう。
試験では指定商材以外の商材を使用すると失格とみなされ、その場で試験は不合格となってしまいます。
受験前には使用商材の申請が必要なため、試験に使う商材は予備用をストックしておくと安心です。
詳しいメーカーおよび商材名は日本ネイリスト協会の公式HPでチェックしてください。
ネイリストが選ぶジェルネイルおすすめは国産品!

身体に長期間塗布するジェルネイルは安全性が重要です。
見た目だけではなく健康面にも配慮して、信頼性の高い国産品の製品を使用しましょう。
しかし、ネイリストが使用するメーカーはプロ用ネイル商材専門店で販売されているものがほとんどです。
実店舗・オンラインストアともにネイリスト資格またはネイルスクールの学生証が必要な場合もしばしばあります。
もちろん、商材によってはセルフネイラーでも購入可能ですが、品数が限られるほか、会員価格で購入できない点はデメリットといえるでしょう。
本格的なネイル用品を使用したいなら、いっそネイリスト資格取得を目指すのもひとつの手です。
ネイルスクールシンシアなら、多数の受賞歴がある優秀なネイリストからネイルの技術や知識を学べます。
新宿のスクールから遠い場合はオンラインスクールも展開しているため、ぜひ一度お問い合わせください◎